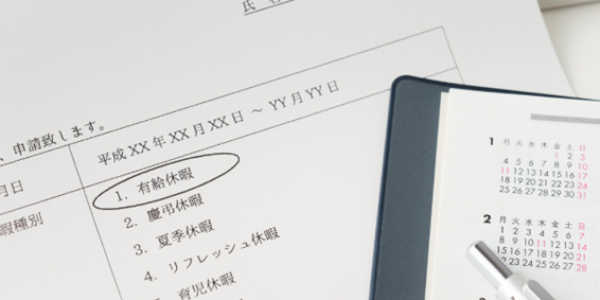事業主が社員を雇用する場合、会社が提供する法的義務が課せられた「法定福利厚生」について理解しておく必要があります。
法定福利厚生の適用条件は細かく定められているため、社員の雇用や増員を検討している経営者の方は参考にしてください。
1.法定福利厚生の種類
法定福利厚生とは、法律で会社が実施を義務づけられている福利厚生のことです。
【法定福利厚生の一覧】
項目 |
概要 |
健康保険 |
社員やその家族が病気やけが、出産、亡くなったときなどに、医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させる目的の制度。 |
厚生年金保険 |
公的年金の1つで、会社で働く労働者が加入する保険給付を行う制度。 |
介護保険 |
高齢化や核家族化の進行などを背景に、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えるための保険制度。 |
雇用保険 |
労働者が失業した場合、生活の安定と就職の促進のための給付を行う制度。 |
労災保険 |
業務や通勤が原因でけが、病気、死亡した場合、国が事業主に代わって給付を行う制度。 |
年次有給休暇 |
一定の要件を満たした全ての労働者に与えられる、取得しても賃金が減額されない休暇制度。 |
生理休暇 |
雇用形態や勤務形態を問わず、すべての女性労働者が取得可能な制度。 |
産前産後休業 |
6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合や産後8週間を経過しない女性が取得できる休業制度。 産後6週間を経過し、医師が認めた女性が請求した場合は就業可能。 |
公民権に関わる休暇 |
労働時間中に、選挙権や公の職務を執行するために必要な時間がある場合に使用できる制度。 裁判員になった社員の休暇など。 |
子の看護休暇 |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員は、年度内で5日を限度として、子の世話を行うための休暇を取得できる制度。 |
介護休暇 |
介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、年度内で5日を限度として、介護を行うための休暇を取得できる制度。 |
出生時育児休業 |
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能な制度。産後パパ育休とも呼ばれる。 |
育児休業 |
子が1歳に満たない場合に取得できる休業制度。 |
介護休業 |
労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休業制度。 |
育児・介護のための短時間勤務 |
育児や介護を行う社員の所定労働時間を短縮する制度。 |
健康診断 |
医師による雇入時および定期健康診断を社員へ実施する制度。 |
前提として知っておきたいのは、雇用した社員に各種社会保険に加入させ、事業主が費用を払うことで、それぞれの保険で定義された「万が一」に備えることができる仕組みを、国が提供し、義務付けているということです。
また、休暇や休業についても、法律にしたがって法定福利厚生を提供するだけで、雇用される社員を適切に休ませることができます。
ちなみに、「福利厚生」は社員が得る給与以外の利益のことです。
法的義務がある「法定福利厚生」のほかに、法律による定めではなく、会社が独自で用意する「法定外福利厚生」があります。
法定外福利厚生には現物給与や待遇まで様々ありますが、社会通念上相当とみなされる要件を満たせば福利厚生費として計上し、非課税にできます。
福利厚生費については次のコンテンツで詳しく解説しています。
福利厚生費とは?定義や類語との違いから非課税要件まで解説
なお、年次有給休暇以外の休暇休業制度は、子の看護休暇や介護休暇など法律で定められた休暇でも、会社には取得させる義務が課せられているだけで、給与の支払い義務はありません。
つまり、年次有給休暇以外の休暇休業は、会社によっては有給休暇か無給休暇かが異なり、就業規則に法定休暇とみなす範囲や必要な手続き、賃金に関する事項を記載する必要があります。
福利厚生における休暇については次のコンテンツで詳しく解説しています。
福利厚生の休暇とは?種類から週休3日制まで基礎知識を解説
また、法定どおりに社員に定期的に健康診断を行い、診断結果に応じた指導を行うことにより、社員の健康上の問題が事業運営に影響しないようにできます。
福利厚生における健康診断については次のコンテンツで詳しく解説しています。
福利厚生の健康診断とは?種類や対象社員、経費の計上方法を解説
2.法定福利厚生の費用負担
事業主は従業員に対して支払う給与以外に、法定福利厚生にかかる費用を負担する義務があり、原則、支払う費用には課税されません。
法定福利厚生にかかる費用やその勘定科目は「法定福利費」と呼びますが、一般的には「法定福利厚生における保険料」に限定されます。
注意したいのは、冒頭の一覧表でも示したとおり、法定福利厚生には休暇や休業、健康診断なども含まれ、社員の雇用時に加入義務のある社会保険だけを指す言葉ではないということです。
つまり、「法定福利厚生の費用=法定福利費」とは言えません。
休暇や休業にかかる費用については、ケースバイケースですが、例えば労働保険の対象となる労働災害(労災)以外の事由で、社員が休業した場合に会社が支給する休業手当は給与として扱われ、課税されます。
参照:No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係|国税庁
健康診断は要件を満たせば福利厚生費として非課税になります。
参照:人間ドックの費用負担|国税庁
2021年(令和3年)度の法定福利費の社員一人あたりの平均額は50,283円ですが、休暇や休業、健康診断などの法定福利厚生の提供には、それ以上かかると想定した方がよいでしょう。
参照:令和3年就労条件総合調査の概況「第18表常用労働者1人1か月平均法定福利費」| 厚生労働省
法定福利費を含めた福利厚生費の平均額については次のコンテンツで詳しく解説しています。
福利厚生の平均費用はいくら?中小企業でよくある制度や施策も解説
法定福利費の負担割合
法定福利厚生に関わる費用の法定福利費は、法定福利厚生の種類によって会社と労働者の負担する割合が異なります。
【法定福利費の負担割合(一般の事業の例)】
法定福利費項目 |
負担額 |
労災保険料 |
事業者が全額負担 |
雇用保険料 |
【事業主負担額】 |
健康保険料 |
事業者が1/2を負担 |
厚生年金料 |
事業者が1/2を負担 |
参照:健康保険法 第百六十一条|e-Gov法令検索
法定福利厚生の適用条件を満たしている労働者の法定福利費を支払っていない場合は、管轄の機関によって、遡って法定福利費を徴収され、追徴金を徴収されます。
そのため、適用条件を満たしている場合は、労働者の雇用形態に関わらず法定福利費の支払いが必要です。
なお、農林水産業や建設業など事業の種類によっては、雇用保険料の負担割合が異なる場合があります。
雇用保険料率について確認したい方は、次の参照先をご確認ください。
参照:令和4年度雇用保険料率のご案内 | 厚生労働省
法定福利厚生は非正規雇用労働者も適用される
パートやアルバイトなどの非正規雇用労働者の場合でも、適用条件を満たしていれば法定福利厚生の対象になります。
法定福利厚生の適用条件は、福利厚生によって異なります。
【法定福利厚生の種類と適用条件】
法定福利厚生 |
適用条件 |
厚生年金 |
・週の所定労働時間が20時間以上 |
年次有給休暇 |
・半年間継続して雇われている |
労災保険 |
・事業者に雇用されるすべての労働者 |
雇用保険 |
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者 |
子の看護休暇 |
・勤続6カ月以上および週の所定労働日数が2日を超える者 |
出生時育児休業 |
・子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6カ月を経過する日までに労働契約満了が明らかでないこと |
育児休業 |
・子が1歳6カ月に達する日までに、労働契約満了が明らかでないこと |
介護休業 |
・介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6カ月を経過する日までに、契約満了することが明らかでない者 |
育児・介護のための短時間勤務 |
・1週間の所定労働日数が2日を超えている ・雇用期間が1年以上 |
健康診断 |
・1年以上の雇用契約、または1年以上引き続いて雇用した実績があること ・1週間あたりの労働時間が通常の労働者の3/4以上であること |
厚生年金や健康保険は、2020年(令和2年)の年金制度改正法の成立により適用条件が変更になりました。
参照:年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました|厚生労働省
年金制度改正法により適用条件が拡大されているため、非正規雇用労働者を雇用している会社は、法定福利厚生の適用範囲の確認が必要です。
年次有給休暇は、労働基準法によって適用条件が定められています。年5日の年次有給休暇の取得も義務付けられており、違反した場合は罰則が科される場合があります。
参照:働き方改革関連法解説 P7|厚生労働省
社員の種類による福利厚生の待遇差については次のコンテンツで詳しく解説しています。
正社員の福利厚生と待遇差がある従業員がいるとき必要な対応とは?
(執筆 株式会社SoLabo)
生22-6592,法人開拓戦略室